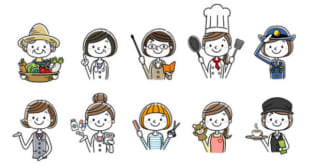金融商品を運用する際の方針として、「特定の指数(インデックス)を上回ること」を目的とするスタイルを「アクティブ運用」というのに対し、「インデックスと同様の投資成果・リターンをあげること」を目指すスタイルを「インデックス運用」といいます(パッシブ運用ともいいます)。その代表的な商品がETF(Exchange Traded Fund、上場投資信託)やインデックス投信でしょう。
この「インデックス運用」の金融商品を買うことのメリットはいくつもあります。まずあまりコストをかけずに分散投資できることが挙げられます。たとえば日経平均に連動したETFを購入することは、日経平均に採用されている銘柄すべてに投資するのと同じ効果が期待できます。これらを比較すると、当然前者のほうが楽ですし、あまりコストもかかりません。
逆にデメリットは、インデックスを上回るパフォーマンスは期待できないことがあります(ただ実際には、アクティブ運用の金融商品のパフォーマンスを上回るものもあります)。分散投資なのでリスクを抑えられる反面、期待できるリターンも低くなります。
ETFはほとんどの証券会社でも買える
インデックスがよく用いられる商品である「ETF」について、「インデックス投信」と比べながら検証したいと思います。
ETFは、日経平均やTOPIXといった株価指数や、金価格、REIT(不動産投資信託)などの指標に連動するよう運用されている、上場投資信託です。こうした代表的な指標はニュースで頻繁に報じられるため、値動きや損益などを比較的把握しやすいと言えます。
投信は購入できる証券会社が限られていることがありますが、ETFは上場しているため、ほとんどの証券会社の口座でも株式と同様に投資できます。
販売手数料は、安いと0.1%程度、保有期間にかかる信託報酬は年間0.1-0.5%程度ですから、インデックス投信(販売手数料0-2%、信託報酬0.5-1%)よりも低めと言っていいでしょう。
投信の値段が決まるのは1日1回、ETFはリアルタイムで変化
株式と同じで、上場している取引所で取引が行われている間(場中)に成行(なりゆき)や指値で発注できます。成行とは売買の価格を指定しない注文方法で、指値とは具体的に「いくらで(買う・売る)」と指定する方法です。値段についても、上場している株式の銘柄と同じで、リアルタイムで変わります。
これに対して投資信託の価格(基準価額)が発表されるのは1日1回です。なぜなら投信は複数の株式や債券などを組み合わせた金融商品なので、構成するそれぞれの価格が決まらないうちには価格が決定できないからです。このため投資家は、売買したい投信の値段が分からないまま取引することになります。
またETFは、資金以上の取引を可能にする「信用取引」もできます。一般の投信とは違って「売り」から始めることもできます。
ここ数年で残高が大きく伸長 日銀も買い入れ
東証に上場しているETF残高は、2016年4月末時点で15兆円です。2011年には2.7兆円でしたから、ここ数年で大きく伸びていることが分かります。投資対象を国内にしているETFが154銘柄、外国ETFが8銘柄、合計202銘柄が上場しています(5月末)。
日銀が金融緩和の手段として、国債だけでなくETFも買い入れていることが度々報じられています。最近でも5月19日、人材や設備投資に積極的な企業の銘柄を組み入れたETFが東証に上場したばかりです。通称「賃上げETF」と呼ばれ、このタイプのETFを日銀が最大で年間3,000億円買い入れる考えです。こうした状況もあって、ETFの注目度は年々高まっていると言えるでしょう。
【関連記事】
・そもそも「株」ってなんだ? 世の中を豊かにした人間の英知 「株・株式会社」
・「円安と円高」についてちゃんと説明できますか? 外貨投資のリターンとリスクとは
・金融サービスを変えるフィンテック
・大手製造業の社内体制変革に注目――GE、シーメンス、日立
・中国不動産、2016年も政府の支援策が続く見通し
 お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく
お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく