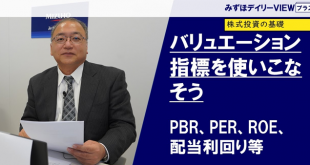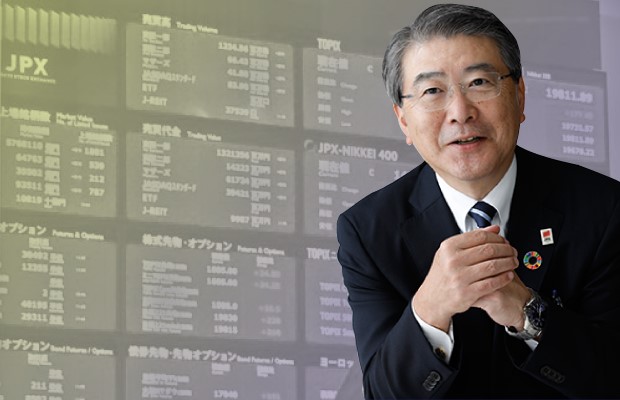
「リズムとハーモニー」
株式のリズムということに結構こだわって相場に接してきました。
続落のあとの反発タイミングが2拍子なのか3拍子なのか。
続伸の限界は奈辺(どのあたりに)にあるのか。
などなどをテーマとして、観察してきました。
分かったことは、同じリズムで動くことは多いけれど、一気にリズムが崩れて別のリズムに移行するという単純なことだけ。
どんな法則で、どんな感じで移行するのかは皆目見当がつきませんでした。
ある時「ハッ」とさせられたのは、巨匠が弟子に向かって「落語を練習するなら俺のリズムとメロディーでしかやってはいけない」と言った言葉でした。
相場にも当然ながらリズム(拍子)だけでなくメロディ(旋律)があります。
リズムだけでは当然見逃しもある筈。
「反復、緊張、解決」というのがメロディならば、相場にも反復・緊張・解決がきっとあるのでしょう。
旋律の上下運動のように株価の上下変動があるのかも知れません。
そして音楽の三要素はリズムとメロディとハーモニー(和音)。
ハーモニーは音の調和ですから、相場のハーモニーだって、たとえば輸出関連と新興株とか、あるいはETFとバイオ株とか意外なところに共鳴があってもおかしくはないでしょう。落語にさえ「リズムとメロディ」があるのですから株にもきっと存在しているに違いありません。
バッハのインベンションとか、あるいは対位法がもしもチャート上に展開しているとしたら、これは結構面白いことなりそうです。
チャートと楽譜を結び付けてみると結構興味深いかも知れません。
印象的な音のつながりを直感的に認識し、メロディとして楽しむように株価の推移や連動を観察・学習することは結構必要な気がします。
このメロディとハーモニーを具体的に体感することから始めること、も大切かも知れません。
そして・・・。
落語の面白さの一つはストーリーの反復。
最初のシーンでのストーリーの立場が逆転する話。
あるいは最初のシーンでのストーリーが通用しない話。
最初のシーンで話の進行がわかるのですが、その逆転の面は絶妙です。
これは株式市場にも通用するでしょう。
一度見た光景が次も一緒になる訳はなく、想像以上の展開になることは多いもの。
あるいは、次の展開では逆になるオチがある場合もあります。
同じストーリーを二度話して通用するほど株の世界もやさしくはありません。
だから同じ進行の立場を変えたり、行方が変わったりするのです。
その意味ではストーリーのリフレインやリピート、転換の行方を日々模索することも必要でしょう。
「粋と野暮」
マーケットは「粋」と「野暮」が対立する場所です。
江戸の粋を落語などで見てみると・・・。
例えば「火焔太鼓(かえんだいこ)」。
「商人というものは、儲ける時に儲けておかんと今度は損ができん」。
あるいは「商人は損をする時もあるから儲けられる時に儲けておけ」。
粋に憧れつつもどうもこの心理は難しいもの。
イケイケドンドンの「粋」。
鈍重に構えてなかなか動かず文句ばかり言っているのは「野暮」とでも言うのでしょうか。
芝の浜で大金入りの財布を拾った怠け者の主人公。
仲間を呼んで大喜びの乱痴気騒ぎの翌朝。
起きてみると、女房氏は「拾った財布なんか知らない」。
以来、酒断ちをして一生懸命に働くようになって3年。
女房氏は財布を出してきて「あれは夢ではありませんでした」。
「こんなに頑張って3年も働いたことだし、久しぶりにお酒でもどうですか」。
しかし主人公。
「よそう。また夢になるといけねぇ」。
落語「芝浜」のくだりです。
株の世界でも「よそう。また夢になるといけねぇ」なんて台詞が聞けるようになるのにはあと何年かかるのでしょうか。
少なくとも20年以上も一生懸命であることは間違いないのですが・・・。
それにしても、江戸って妙に魅惑的な時代。
「宵越しの銭は持たねぇ」なんて格好よさ。
だから「大つもごり(大晦日)」が緊張感のある妙な化かしあいと言い訳合戦。
「宵越しの金は持つ」人ばかりが増えて時代は面白くなくなったのかも知れません。
ところで江戸の粋の仕草というのがいろいろあります。
★「七三の道」
自分が歩くのは道の3割にして残りの7割は人のために空けておくこと。
これを相場で実現しようとすると難しいでしょう。
★「ロクを利かす」
第六感を磨くことは相場にも通じます。
★「打てば響く」
気配りをして即行動する機敏さは相場にも求められます。
加齢とともに響かなくなるのが怖いところです。
★「時泥棒」
むしろ相場に時間を奪われているような気もしますが・・・。
★「こぶし腰浮かせ」
乗り合い船などで後から来る人のためにこぶし一つ分腰を浮かせて席に座ること。
相場で言えば「頭と尻尾はくれてやれ」でしょう。
★「陽に生きる」
相場で「陽」だと報われることは少ないものですが・・・。
★「ムクドリ」
大群で押し寄せ、しばらくするとどこかへ消えるのがムクドリ。
昨今では「イナゴ」とも言われます。
★「お心肥やし」
自分の心も常に豊かに思いやること。
これも相場では報われることが少ないものです。
★「束の間つきあい」
塩漬け以外は皆これでしょうか。
★「肩引き、傘かしげ」
これを相場で実行すると負けてしまいそうです。
こう見てくると相場で「粋」に振舞うと、どうしても浅葱裏(あさぎうら)の「野暮」には叶わないような印象。
たぶんマーケットで重要なのはさまざまな「雑音」を取り除く作業。
瑣末(さまつ)な雑音に耳を傾けるから「夜明けの行灯(冷静になる)」になれないのでしょうか。
幕末1860年に幕府使節の小栗忠順らの一行がブロードウェイを馬車で行進しました。
そのときに詩人ホイットマンが作ったとされる「ブロードウェイの華麗な行列」。
「西の海を越え、はるかなる日本からアメリカに渡ってきた。顔は日焼けし、刀を二本さした礼儀正しき使節よ。幌もない馬車上に身をゆだね、帽子も被らずに堂々と
この日マンハッタンの街をゆく」。
東京株式市場もこれくらいの誇りを持ちたいものです。
櫻井 英明(さくらい えいめい)
ストックウェザー「兜町カタリスト」編集長
日興証券での機関投資家の運用トレーダー、「株式新聞Weekly編集長」などを経て、2008年7月からストックウェザー「兜町カタリスト」編集長。
幅広い情報チャネルとマーケット分析、最新経済動向を株式市場の観点から分析した独特の未来予測に定評があり、個人投資家からの人気も高い。
【おすすめ記事】
・東京五輪の経済効果は?その後の落ち込みはどうなる?
・転職前に気を付けておきたい税金・年金・お金の話
・知っていますか? 「年金」の種類と仕組み
・お金のことが学べる映画5選
・2020年に向けて市場規模が急拡大 「VR」「AR」で世界はどう変わる?
 お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく
お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく