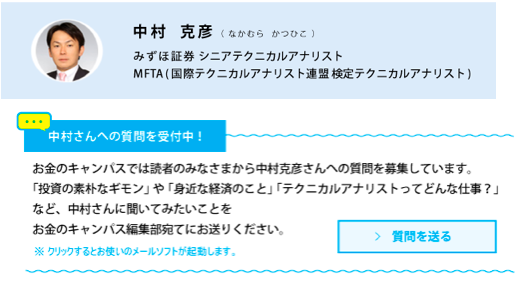日本株の下げ基調はいつまで? 7月の<中村克彦のテクニカルコラム>
今、気になる相場の話題をみずほ証券の中村克彦さんにわかりやすく解説してもらうこのコラム。
梅雨が明け、本格的な夏が到来です。気象庁による発表によると、2018年の夏は例年よりも晴れの日が多く、猛暑になりそうだと予想されています。その一方で株式相場は5月下旬からぐずついてはっきりしない展開。下げ基調はいつまで続くのでしょうか?中村さんに聞いてみました。
株式市場の梅雨明けはいつ?
―― ここのところの日本株は少しさえない値動きが続いていますね。保有している株も値下がりしてしまって、気持ちもどんよりです。
7月に入ってからの日経平均株価は下げ基調ですね(7/6時点)。
背景には日銀短観の悪化や米中貿易摩擦の警戒感がくすぶっているという状況があります。しかし、年金マネーとみられる長期資金が日本株の下値を拾っています。テクニカル指標の一部では売られすぎの水準に近づくなか、戻り売りもそろそろ山場を通過しそうです。7月の日本株は遅めの梅雨明けとなるか。今後の見通しを探ってみましょう。
―― よろしくお願いします。
日本株の動向を知るには年金マネーの動きがカギ?
(画像=PIXTA)
今の日本株の動向を知るうえで無視できない存在が“年金マネー”の動きです。
私たちが納めている厚生年金や国民年金などの年金マネーは、ただ積み立てるだけではなく株式や債券などの売買を通じて運用されていて、その収益は、年金のための財源に充てられることになっています。
少子高齢化が進む日本において、給付金の確保と現役世代の負担を軽くしようという目的です。
その運用を任されているのがGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)というところです。
―― 将来年金なんてもらえないかも!? …なんて思ったりしますが、運用成績が良ければ安心できます。GPIFには頑張ってほしいですね~。
GPIFの発表によると2001年度以降の平均収益率は年率+3.12%、累積収益額は+63.4兆円ですから、着実に年金財源は増えているのでひとまずはご安心を。実は、GPIFは156兆円もの巨額マネーを動かす“世界最大の機関投資家”なんです。
―― 156兆円!? 市場での影響力も大きそうです。
そうですね。GPIFの売買動向は、「信託銀行」の売買動向を見ればわかるといわれているので早速見てみましょう。
信託銀行が大きく買い越す、2年ぶりの大きさ。日本株への影響は?
GPIFは、基本ポートフォリオ(国内債券35%、国内株式25%、外国株式25%、外国債券15%)に従って機械的な売買を行っています。目先の運用益を追わずに長期分散投資の効果をねらい、リスクを抑えながら期待収益率を上げています。
その投資スタンスは徹底した“逆張り”です。2015年夏の中国人民元切り下げ、2016年前半の原油急落やBREXIT(英国のEU離脱決定)を振り返っても、日本株の下落局面で大きく買い越しています(図中①)。
―― 下がったときに買って、その後上昇に転じていますね。
その後の運用資産額は、2017年3月末が144兆円、2018年3月末が156兆円と膨らみ、実績を順調に積み上げています。
そして2018年6月、米中貿易摩擦激化を警戒し、日本株は下げ基調でしたが、信託銀行は日本株を4,420億円も買い越しました。このような大幅買い越しは約2年ぶりです(図中②)。
一方、同期間での海外投資家は6,641億円も売り越し、逆の動きをしました。日本株の売買シェアの7割を握っている海外勢ですが、その大半は短期売買を繰り返すヘッジファンドが占め、投資スタンスは“順張り”の傾向が強いです。それだけに海外勢のさらに後追いとなる順張りには注意したいところです。つまり、売買動向に関しては、海外勢よりも信託銀行が堅実な運用へつながるモノサシとなりそうです。
―― 買いを入れるタイミングの参考になりそうですね。
違う側面から日本株の動向を探るため、需給の状況を見ていきましょう。
信用評価損益率▲15~▲20%前後は売られ過ぎ、いったん売り一巡も
需給を知るためには「信用評価損益率」が参考になります。
(信用評価損益率をおさらいするには【よくわかる信用取引~「回転日数」「信用評価損益率」とは?】をご覧ください。)
日経平均株価は2018年1月23日に高値24124円をつけてから、まもなく6ヵ月が経ちます。制度信用取引の持ち高は6ヵ月以内に解消する必要があるため、今年1月に株式を買い建てた投資家は7月に入って「反対売買」しなければならない期日が近づいています。
―― そろそろ決済のための売りが落ち着いてくる頃ということですね。
その信用取引をしている投資家がどれくらい含み損益を抱えているかをあらわす「信用評価損益率」を押さえておく必要もありそうです。これは相場全体の地合いをみる重要な指標のひとつで、信用評価損益率は通常▲5%~▲20%の間で推移する傾向がみられるため、相場の天底を推し測ることもできます。とくに底値圏のサインとして使える指標です。
2018年6月29日申込時点での信用評価損益率は▲11.57%です。
その後7月2日、日銀短観の悪化等を背景に、日経平均株価は一時500円超も下げました。それゆえ、信用評価損益率は売られすぎの水準となる▲15%近くまですでに悪化していそうです。今後は売り一巡感が台頭してくることもあるでしょう。
―― 目先の需給は回復しそうな雰囲気はありますね!日銀短観が悪化したことはすこし気がかりですが…
日銀短観は悲観しすぎなくてもよい?
日銀短観をつぶさにみると、景気の先行きを示す設備投資は明るい兆しもうかがえます。
全規模・全産業による設備投資計画が市場予想の中央値4.2%増に対し、7.9%増と大きく上回りました。主要28業種のうち、15業務が2ケタ増加を見込んでいます。
また、2018年度の大企業製造業の想定為替レートは前回調査の1ドル=109円66銭に対し、6月調査は107円26銭でした。足元の円相場は1ドル=110円前後で円安方向に推移していることから輸出関連企業中心に収益の押し上げ要因へつながりそうです。
7月中旬からは国内企業決算が始まるため、業績面から日本株の見直し買いも期待されるでしょう。また、7月下旬には信用取引における高値期日(6ヵ月)が明けてくることから、戻り売り圧力も徐々に和らいでくるのではないでしょうか。
以上のことから今回のポイントをまとめると、
① 日本株の下値を信託銀行経由で年金マネーが買っている。
② 信用評価損益率が売られすぎの水準に近づきつつあるなか、過度な悲観見通しは控えておきたい。
③ 国内企業の決算発表をきっかけに日本株の見直し買いが下支えよう。
④ 信用の高値期日明けが需給改善を後押しすれば、7月相場は戻りを強めると思われる。
ということになります。
―― 今年は“夏枯れ”しないことを期待します。今月もありがとうございました!
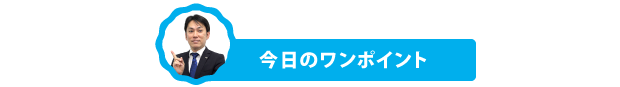 GPIFと信託銀行
GPIFと信託銀行
巨額のお金を運用するGPIFですが、四季報の大株主欄を見るとその名前は見当たりません。なぜかというとGPIFは信託銀行を通じて株を取得しているからです。そのかわり、「日本トラスティ・サービス信託銀行」「日本マスタートラスト信託銀行」「資産管理サービス信託銀行」といった信託銀行の名前が大株主として掲載されているのをよく見かけると思います。GPIFが直接大量保有していることが公になりすぎると、市場の公平性をそこなう可能性があり、このように信託銀行を通じて運用されています。
>>【連載】これからの相場をテクニカル視点で読む! 中村克彦のテクニカルコラム
毎月更新!直近の相場を、テクニカル分析を使ってわかりやすく解説!
>> 基礎からわかる「テクニカル分析」入門 レッスン一覧へ
テクニカル分析をじっくりと学びたい方はこちら
【動く中村さんはこちら!】
相場のポイントを動画でも詳しく解説しています。みずほマンスリーVIEWは毎月・ストックボイスは毎週火曜日に更新されるので、投資の参考にぜひ活用してみてくださいね。
※みずほ証券の公式YouTubeサイトに遷移します。
メール送付にあたってのご注意
本企画にかかる質問メールは、お金のキャンパスのスポンサーであるみずほ証券株式会社(以下、みずほ証券)に送信されます。みずほ証券は、本企画で得たお客さまからの質問内容を今後の配信記事に反映するほか、登録された個人情報を、ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービス等に関する各種ご提案やご案内のために利用することがあります。詳細は、みずほ証券「お客さまの個人情報の取り扱いに係る利用目的」にてご確認ください。
【おすすめ記事】
・東京五輪の経済効果は?その後の落ち込みはどうなる?
・転職前に気を付けておきたい税金・年金・お金の話
・知っていますか? 「年金」の種類と仕組み
・お金のことが学べる映画5選
・2020年に向けて市場規模が急拡大 「VR」「AR」で世界はどう変わる?
 お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく
お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく