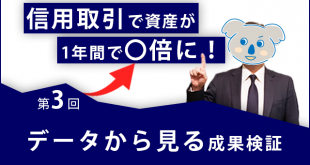もし2005年から毎月初めに、日経平均株価に連動する投資信託を1万円ずつ買っていたら、どのような結果になっていたでしょうか。
2005年1月4日から毎月初めの日に1万円ずつ積み立てたとします。2016年4月1日まで行ったとすると、136ヶ月ですから合計で136万円です。いまは金利がほとんどつきませんので、今回は金利分を考慮しません。
それに対して、毎月初めの平日の日経平均株価の終値で1万円ずつ投資したとしましょう。投資元本は先ほどの積み立て金額と同じく136万円ですが、2016年4月15日の日経平均株価の終値である1万6,848円3銭でそれまでに購入した金額を評価すると、186万6,971円となります。
つまり、毎月1万円ずつ積み立てた場合と、毎月1万円ずつ日経平均株価に連動する投資信託を買った場合では、50万6,971円の差が生じたことになります。税金や諸費用を考慮しなかった場合のリターンは+37.28%です。さらに税金や諸費用を差し引いたとしても、この条件においては十分利益が出ていることでしょう。
これがもし136万円といった多額の投資金額を、一気に投じていたら同じような結果が得られたでしょうか? もちろん株価が急上昇した時に売り抜ければ、大きな利益が出せたかもしれません。
しかし、株価は大幅に下落することもあります。2008年9月15日には米投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに世界の株式市場は激しく変動し下落し始めました。世界的な金融危機のリーマン・ショックの始まりです。それまで1万2,000円台だった日経平均株価は10月28日に一時7,000円台を割るなど、4割を超える下落に見舞われました。もしリーマン・ショック直前に多額の投資金額を株式市場に一気に投じていたらどうなるでしょうか? その投資金額は一気に減ってしまったのではないでしょうか。
一度にまとまった資金で投資を行うベストなタイミングは、誰にも分かりません。しかし、投資するタイミングを分け、毎月コツコツ購入していくことは相場急変時に大きく損失を被るリスクを抑えていくことが期待できます。
ドル・コスト平均法は少額からコツコツと投資が可能
定期的に同じ金額をコツコツと投資していく方法は、「ドル・コスト平均法」といって一般的な投資手法の一種です。
同じ金額を投資するので株価が低い時は多く購入でき、株価が高い時は購入できる量は少なくなります。そのため、平均購入単価をならすことができ、高値で買ってしまうリスクを減らせます。長期に継続投資ができる方にはよい投資方法といえるでしょう。
ただし、最終的には株価が上昇していなければ損失が発生することには注意が必要です。
2005年以降にコツコツと投資し、結果がプラスとなっているのは、2016年4月時点の株価の方がそれまでの平均株価よりも高くなっているからです。
例えば、2005年1月4日の日経平均株価は1万1,517円75銭、2009年3月2日の日経平均株価は7,280円15銭でした。こうした株価から見れば、2016年4月15日の日経平均株価1万6,848円3銭の方が圧倒的に高くなっているため、最終的に利益が出せたといえます。
これがもし、リーマン・ショック後のように日経平均株価が8,000円以下に下落するといった状況になっていれば、当然損失が膨らみます。そのため、最終的に株価が上がるタイミングまで投資を継続できるかどうかがポイントです。
この他、株価が安い時にまとめて購入できれば、その方がリターンも大きくなる点も指摘できます。仮に2005年1月4日に136万円分を日経平均株価に投資していたら、2016年4月15日の終値で198万9,392円となっています。
ドル・コスト平均法の結果よりも増えていることがお分かりになることでしょう。これは2005年1月よりも2016年4月に日経平均株価が上昇しているためですが、2009年3月には大幅な評価損を抱えてしまいました。
このように安いと判断して投資したとしてもその後大幅な下落に見舞われるなどベストな投資タイミングを計ることは大変難しいものです。こうした判断が難しい場合には、ドル・コスト平均法でコツコツ行っていくことは理に適っているといえます。
「分散投資」を考える
ここで考えたいのが、ドル・コスト平均法は「時間分散」はできているものの、他の分散ができていないことです。一つの株式ですと、何かあった場合には株価が大きく下落し損失を被る可能性も大きくなります。
日経平均株価は225社の株価の平均ですから、すでに複数の企業への分散投資はできているといえますが、日本国内の企業だけとなります。そのため、さまざまな分散を行うことでさらなるリスク低減を図るような運用も心がけたほうが無難といえます。
例えば、株式だけではなく債券にも投資を行う、日本だけではなく米国も投資対象とするなど、商品や国・地域、通貨なども分けることでリスクを減らすことができます。もちろん、ドル・コスト平均法も活用して購入時期も分散すると、さらにリスクの低減を図ることが期待できるでしょう。
こうした分散投資は昔から言われていることであり、「卵を一つのカゴに盛るな」という格言があるほどです。一つのカゴにまとめていると、カゴを落としたら卵がすべて割れる可能性があります。しかしカゴを複数に分ければ、一つ割れても他の卵は大丈夫です。これは投資でもあてはまります。
著名投資家も分散投資を勧めています。例えば、世界第2位の富豪であるウォーレン・バフェット氏は、「投資をされる方々の99%以上は、徹底した分散投資を心がけるべきです」と話をしていますし、バフェットの師であるベンジャミン・グレアム氏(1894-1976)も「大半の投資家は個別銘柄など選ぶ必要などないということを繰り返し申し上げておいたほうがいい」と言っています。
そうはいうものの、ある程度まとまった資金がなければより多くの銘柄に分散投資を拡大するのが難しいのも事実です。そこで、プロが分散投資を行う投資信託や複数の企業の株式などを組み込んだETFなどを活用する方法があります。グレアム氏も「自分でうまく銘柄選びができるのは、ほんの数パーセントの投資家にすぎない。もしかしたら、みんながインデックスファンドの力を借りるのが理想なのかもしれない」と述べているほどです。
日経平均連動型の投資信託でまずは投資してみる?
インデックスファンドの代表例は、日経平均株価などの指数に連動する投資信託やETFです。この投資信託を購入するだけでも少なくとも日本株式の中で分散投資が可能です。
まずは、時間分散のできるドル・コスト平均法で投資を検討してみるといいかもしれません。そして、少しずつ投資する金融商品の幅を広げ、さらなる分散投資につなげれば、リスクを抑えていくことが期待できるのではないでしょうか。
【関連記事】
・そもそも「株」ってなんだ? 世の中を豊かにした人間の英知 「株・株式会社」
・「円安と円高」についてちゃんと説明できますか? 外貨投資のリターンとリスクとは
・金融サービスを変えるフィンテック
・大手製造業の社内体制変革に注目――GE、シーメンス、日立
・中国不動産、2016年も政府の支援策が続く見通し
 お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく
お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく