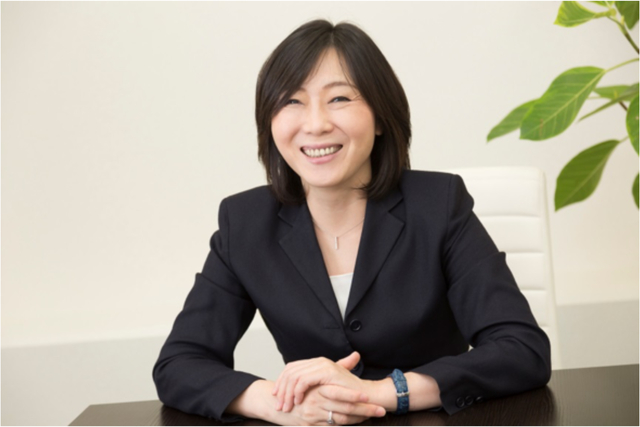
マイナス金利に突入した現在、大切なお金を守り、増やしていくために資産運用を考えている方は多いのではないでしょうか。お金のキャンパスでは、生活経済ジャーナリスト/ファイナンシャル・プランナーの和泉 昭子氏による連載を通じて、かしこく資産運用するためのノウハウをお届けします。
第8回目は、日ごろはなかなか考えることを先延ばしにしてしまいがちな「相続」について、いざというときに後悔しないためにやっておくべきことを和泉先生に教えていただきます。
ますます重要になっている相続対策
2015年1月、相続税が引き上げられました。その背景には、資産額が多い高齢者世帯から若い世代への資産の移転を促そうという国の政策方針があります。相続税を上げるかわりに、「教育資金の一括贈与非課税」、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税」、「住宅取得等資金の一括贈与非課税」などの制度を設け、早い時点で子や孫に資産を贈与することで優遇が受けられるようになったのです。
こうしたこともあり、相続税対策などで贈与を使ってあらかじめ資産を動かしておこうと考える方も増えているようです。
生きているうちに相続対策。何からはじめれば?
相続は何からはじめるべきかというと、まずは相続税がかかるのか、かからないかを見極めることです。ご存知の通り、相続税がかかる方はごく一部で、そのほとんどが地価の高い都市圏に集中しています。
相続税がかかる場合には、対策を講じましょう。
保険を使った相続対策
節税対策としてよくいわれるのは、ご自身を被保険者とした保険を使う方法です。生命保険の受け取りには相続税の非課税枠が設けられているので、受け取った保険金の金額が非課税枠の範囲内であれば、相続財産には加算されないのです。
たとえば、相続財産が3,000万円、妻と子どもが2人いるケースについてお話します。この場合、相続人は3人ですから、500万円×3で1,500万円が非課税になり、相続財産は1,500万円とみなされます。つまり、非課税で1,500万円の財産を移転したのと同じことになるのです。
ただし、70歳を過ぎると、健康上のリスクから、大きな金額の生命保険に加入できない可能性もあります。その場合は、ほかの家族を契約者とし、その保険料を1年間で110万円まで非課税となる従来の「暦年贈与」の枠を使って贈与するといった方法もあるので、専門家に相談するといいでしょう。
老後資金の計算も忘れずに
また、相続税を計算すると同時に行うべきことは、ご自身の老後資金がどれくらい必要なのか計算することです。70歳以上の方でしたら余裕をみて100歳ぐらいまでの老後資金を見積もり、残りの資金の範囲内で贈与するようにしてください。
遺産で揉めないために「公正遺言書」
さて、もうひとつ考えておきたいのは、遺された家族が遺産で揉めることがないよう準備しておくことです。法定相続分は決められていますが、人によってさまざまなご希望もおありだと思います。その際、有効なのが遺言書を作成して意志を遺すことです。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、遺言者が口述したものを公証人が筆記し、本人・証人・公証人が署名・押印して作成する「公正遺言書」にした方がいいといわれます。
必ず遺言書を作成しておいた方が良いのが、お子さんがいらっしゃらないケースです。夫が亡くなったら遺産はすべて妻が相続すると思われがちですが、とくに遺言がない場合、法律的には、妻が相続できるのは4分の3で、残りの4分の1は夫の兄弟が相続することになってしまいます。
父や母のどちらかが先に死亡した際の一次相続の場合、配偶者控除があるので、多くの場合、税金はかかりませんが、残されたもう一方の親も死亡したときに子どもだけで行われる二次相続の場合には配偶者控除がないため、課税される確率は高くなります。遺された家族のライフプランなども考慮しつつ、プロに相談しながら遺言書を作成することをおすすめします。
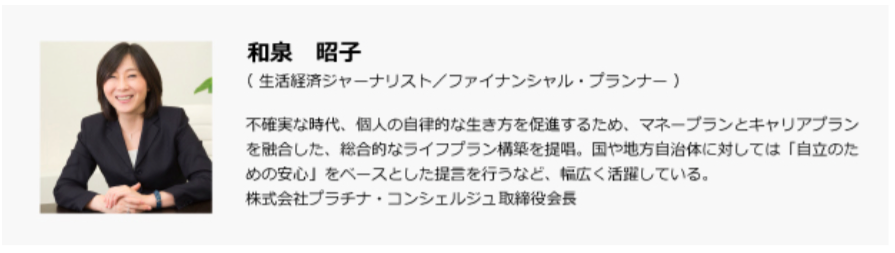
【おすすめ記事】
・【第1回】和泉昭子氏が教える、初心者のための「株式投資入門」
・【第2回】和泉昭子氏が教える、「子のため・孫のためにしっかりお金を残す方法」
・【第3回】和泉昭子氏が教える、「年金減少時代にお金を確保する年金投資術」
・【第4回】和泉昭子氏が教える、「長期保有でうまみのある銘柄選びのコツ」
・【第5回】和泉昭子氏が教える、「進路別・子ども1人にかかる教育費用とかしこい貯め方」
・【第6回】和泉昭子氏が教える、「老後を迎えるまでに今から準備するお金の話」
・【第7回】和泉昭子氏が教える、「少額からはじめる資産運用とドル・コスト平均法」
 お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく
お金のキャンパス 金融や経済のことをもっとわかりやすく


